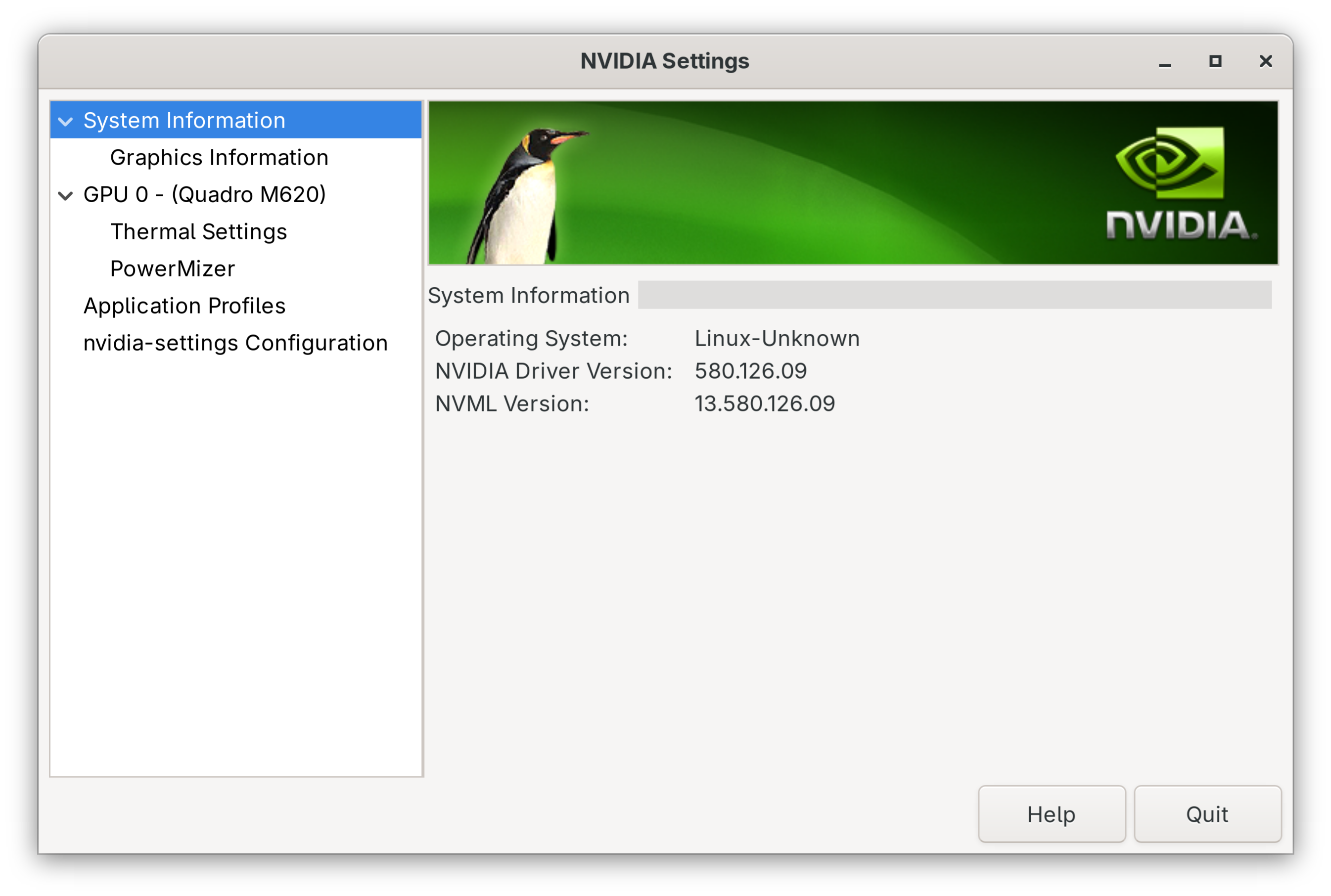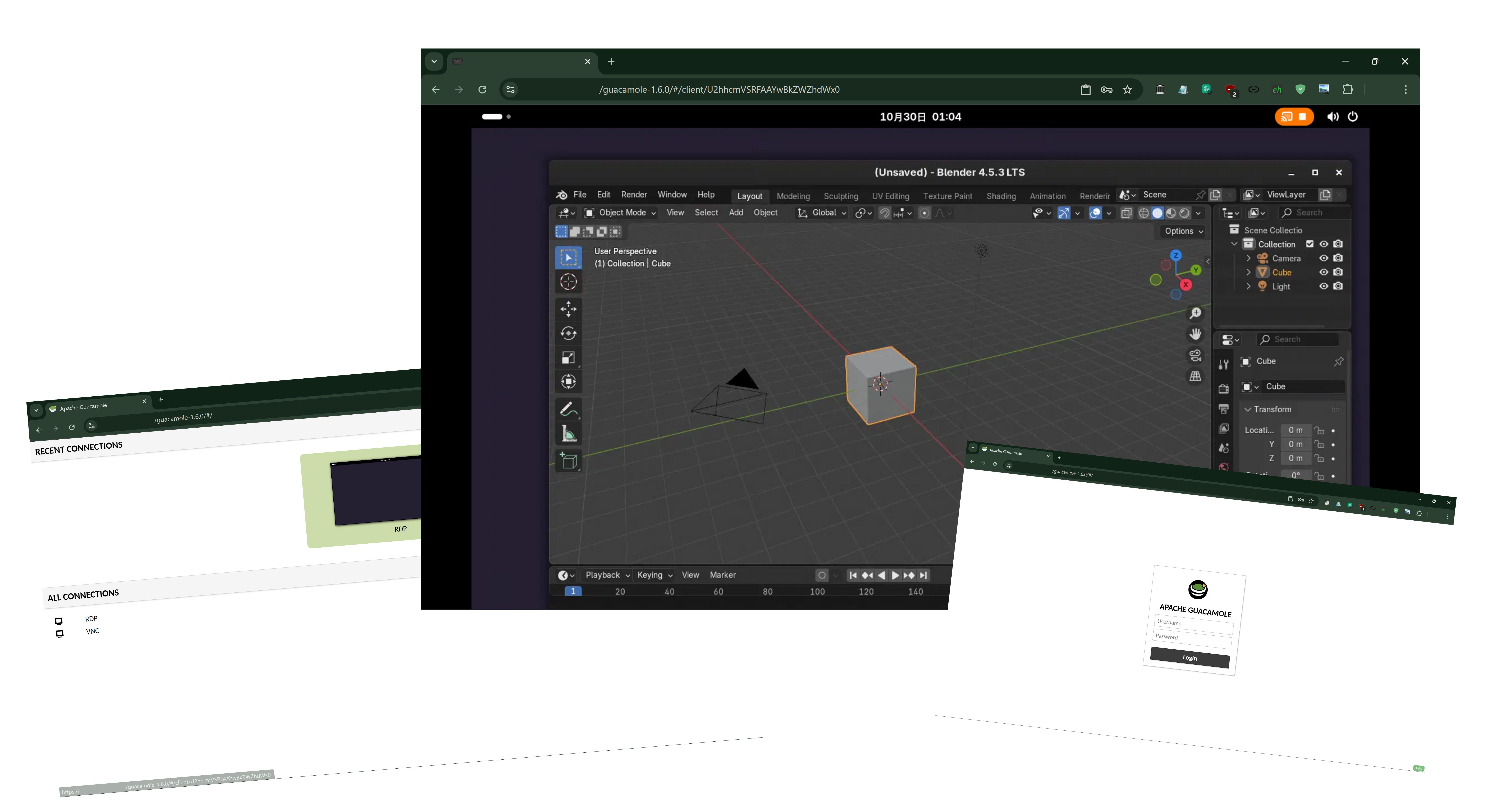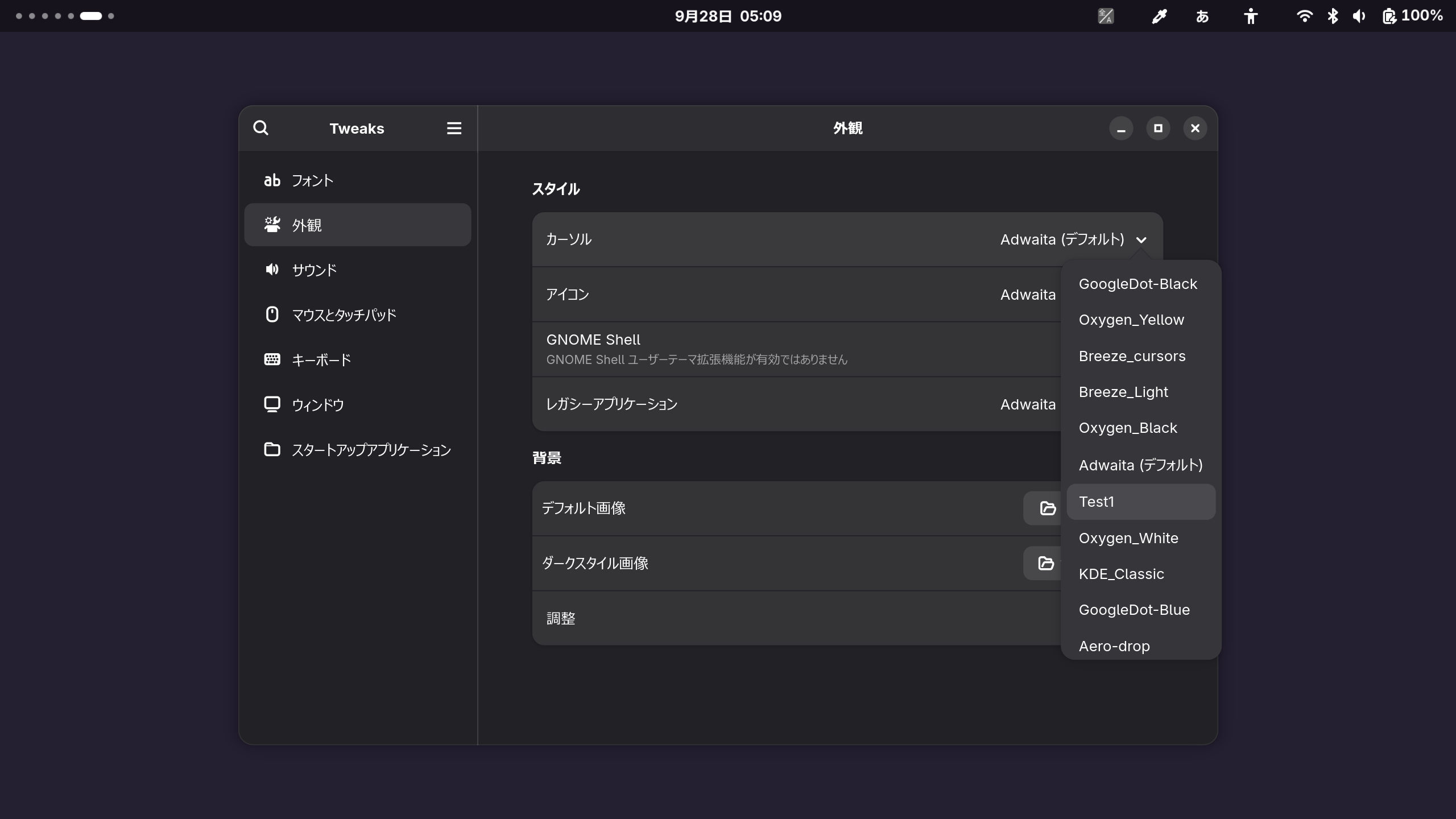mDNSでwindowsに対してlinuxクライアントから名前解決をしたい
この記事を作った動機 LinuxクライアントからWindows側にRDP接続などをするとき、いちいちIPアドレスを直接入力しているのは気持ち悪いと思っていた。今まではそれでいいやと放置していたが、最近いい加減どうにかしようということで、具体的な解決を試みようと思って、案の定手間取ったので記録する。 具体的には、mDNSを使って、Linuxクライアント側から、WindowsクライアントのプライベートIPアドレスを割り出したいということをしていた。基本的には以下のポイントがあった。 ファイアウォールの設定で、mDNSを受け付けるようになっているか? Linuxクライアントに必要なパッケージがインストールされ、必要なデーモンが動いているか? 接続先対象としてのWindows側のホスト名は間違っていないか? Linux側から名前解決を試みるとき、.localのTLDをつけ忘れていないか? 環境 前提としては、個人的なLAN内での利用を想定している。今回は、パブリックネットワーク向けのセキュリティー重視という観点では書いていない。 また重要な前提として、接続先と接続元は、同じプライベートネットワークに属していることとする。 接続先 (Windows) Windows 11 24H2 を使っている 接続元 (Linux) NetworkManger を使っている systemd-resolved を使っていない、無効にしている GNOME 環境 arch linux 環境 仮定 今回は説明のために以下の仮定をしている。Linux側に関しては、/etc/hostnameにすでに適切なホスト名が設定されているという前提である。 Windows側 ホスト名: WinHost IPアドレス 192.168.1.33 Linux側 ホスト名: LinuxHost IPアドレス 192.168.1.55 設定手順 Windows側 (接続される側、mDNSで名前解決される側) ファイアウォールの設定を確認する 今回はmDNSだけでなく、そもそも接続されているか確認するために、pingも通るように設定する。 ネットワーク探索が無効になっていないか確認する Linux側 (接続を試みる側、mDNSで名前解決をしようとする側) パッケージのインストール yay -S avahi nss-mdns # pacman -S avahi nss-mdns デーモンの有効化 sudo systemctl enable --now avahi-daemon.service /etc/nsswitch.confを設定する 以下はAvahi - ArchWikiを参考に設定した一部の例である。今回は IPv4 を対象として、mdns4_minimalを指定した。試してはいないが、mdns_minimal、mdns、mdns6_minimal(IPv6)としても、Avahi - ArchWikiを見る限り設定できる模様である。 ...