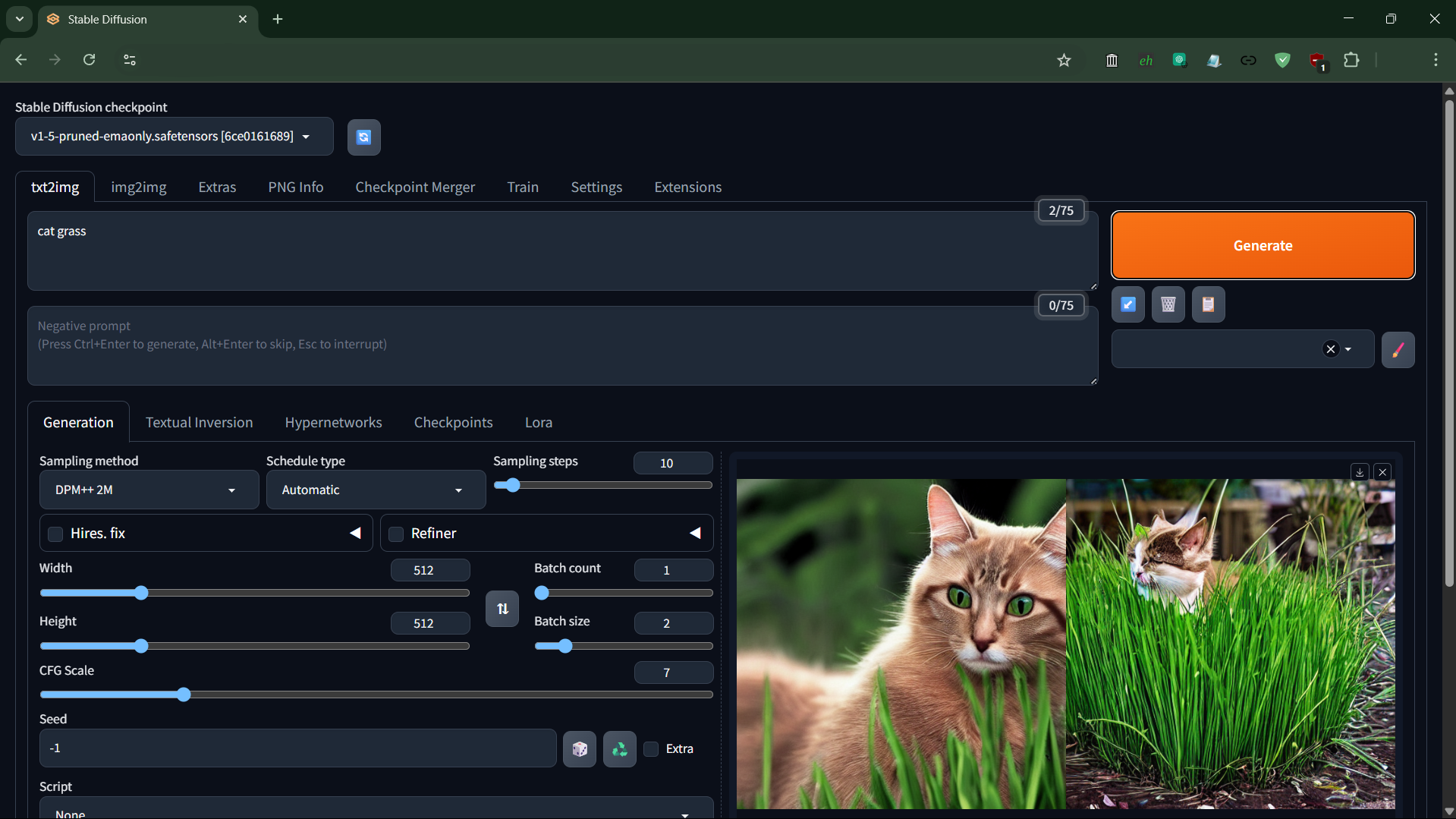この記事を作った動機
なんか最近 AUR に Stable Diffusion WebUIが出現していて気軽に試せそうだったのでインストールして使ってみたということがあった。
その過程で記録しておきたいことがあったので、Stable Diffusion WebUI の導入過程とともに記事を書こうと思った。

環境
System Details Report
Report details
- Date generated: 2025-07-13 20:41:10
Hardware Information:
- Hardware Model: HP ProLiant DL60 Gen9
- Memory: 32.0 GiB
- Processor: Intel® Xeon® E5-2620 v4 × 16
- Graphics: Unknown ※ GTX1080ti
- Disk Capacity: 30.0 TB
Software Information:
- Firmware Version: U15
- OS Name: Arch Linux
- OS Build: rolling
- OS Type: 64-bit
- GNOME Version: 48
- Windowing System: X11
- Kernel Version: Linux 6.15.5-arch1-1
導入
yay コマンドでインストール
yay -Sy stable-diffusion-webui
コンフィグの場所
/etc/stable-diffusion-webui/webui.conf
コンフィグの設定例(webui.conf)
DATA_DIR は専用にディレクトリを作り、変更した方がいいかもしれない。デフォルトの場所だと、モデルを配置したり出力された画像などにアクセスしずらい。
デフォルトだと、"/var/opt/stable-diffusion-webui/data"配下にモデルを配置する場所や、生成した画像が置かれてしまう。都合に合わせてユーザのホームディレクトリとか、適当な場所に専用のフォルダを設けた方が便利ではある。
# Flags to pass to the `accelerate launch` command
# See: https://huggingface.co/docs/accelerate/package_reference/cli#accelerate-launch
ACCELERATE_FLAGS="--num_cpu_threads_per_process=6"
# Flags for stable-diffusion-webui
# See: https://github.com/AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui/wiki/Command-Line-Arguments-and-Settings
#
# Example: WEBUI_FLAGS="--listen"
WEBUI_FLAGS="--listen --api --api-log --xformers --lowvram --disable-safe-unpickle --enable-insecure-extension-access"
# Path to save model files and outputs
DATA_DIR="/var/opt/stable-diffusion-webui/data"
サービスを設定し起動
sudo systemctl enable --now stable-diffusion-webui # 起動と有効化の両方
# sudo systemctl enable stable-diffusion-webui // PC が起動したときに立ち上がるようにするだけの時
# sudo systemctl start stable-diffusion-webui // 単に webui を起動するだけ
この時点で、localhost:7860からは、webui にchromeなどからアクセスできると思われる。正しく起動していれば、とりあえず何か生成できるか試すこともできる。
httpd のプロキシ設定
私の場合はデータサーバとして専用に設けているPCに、今回 stable diffusion webui をインストールしたので、localhostだけで動かれるといちいちリモートデスクトップか何かで、直接サーバ内部の GUI 環境に入る必要があり不便であった。
なので、httpd のプロキシ機能を使って、プライベートなLAN内だけで運用している専用のドメイン名でアクセスされると、localhost:7860として転送するように設定した。
この方法であれば、firewalld などの設定をわざわざ変えなくて済むという点からも管理的な意味合いでは都合がいい。
注意点としては、httpの設定だけでなく、websocket も localhost:7860 に転送する設定が必要であるというところがある。また、httpd 側の専用のモジュールも有効化が必要である。また今回は SSL の設定も混じっているが、そこについては大変すぎるので説明は省くことにする。
- /etc/httpd/conf/httpd.conf (モジュール周りの設定)
# 設定項目自体はすでに "#" でコメントアウトされて存在するので、必要な項目の行の "#" を消すだけでよい。
...
# 必要なモジュールの有効化
LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so
LoadModule proxy_http_module modules/mod_proxy_http.so
LoadModule proxy_wstunnel_module modules/mod_proxy_wstunnel.so
LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
# 必要な設定の書いてあるコンフィグファイルの有効化
Include conf/vhost/service.conf
# オプション
LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so # SSL の設定。一応ここは載せておく
...
- /etc/httpd/conf/extra/httpd-vhosts.conf (プロキシ設定本体)
...
<VirtualHost *:80>
# SSL (HTTPS) の設定なので今回はあまり関係がない
ServerName stable.internal.domain.name
Redirect permanent / https://stable.internal.domain.name/
</VirtualHost>
<VirtualHost *:443>
ServerName stable.internal.domain.name
# SSL (HTTPS) の設定なので今回の設定とはこの 3行はあまり関係ない
SSLEngine on
SSLCertificateFile "/etc/httpd/conf/ssl/stable.internal.domain.name.pem"
SSLCertificateKeyFile "/etc/httpd/conf/ssl/stable.internal.domain.name-key.pem"
# websocket 転送設定
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP:Upgrade} =websocket [NC]
RewriteCond %{HTTP:Connection} upgrade [NC]
RewriteRule ^/(.*) "ws://localhost:7860/$1" [P,L]
# HTTP 転送設定
ProxyPreserveHost on
ProxyRequests off
ProxyPass / http://localhost:7860/
ProxyPassReverse / http://localhost:7860/
</VirtualHost>
...
モデルや生成画像の場所
✅
# DATA_DIR="/home/username/Documents/AI" の場合
/home/username/Documents/AI/models/Stable-diffusion # モデルを配置する場所
/home/username/Documents/AI/outputs # 生成された画像の場所
# デフォルト設定の場合
/var/opt/stable-diffusion-webui/data/models/Stable-diffusion # モデルを配置する場所
/var/opt/stable-diffusion-webui/data/outputs # 生成された画像の場所
## hint
# @ /etc/stable-diffusion-webui/webui.conf
# Path to save model files and outputs
# DATA_DIR="/var/opt/stable-diffusion-webui/data"
# @ /usr/lib/systemd/system/stable-diffusion-webui.service
# destdir="${DATA_DIR}/models/Stable-diffusion"; \
❌
/usr/share/stable-diffusion-webui/models/Stable-diffusion
/opt/stable-diffusion-webui/models/Stable-diffusion
追記
(2025/9/14)
最近気づいたこととして、VRAM の残りがたくさんあったりするのに、GPU が全然使われてなかったり、70GB くらいあるメインメモリを画像生成ごとに徐々にメモリリークして全部食いつぶし、結果的に linux 環境では完全にシステム全体をフリーズさせてしまい、強制的に再起動しないと復帰しないということがあった。
そこで気づいたことややったほうがいいことがわかったのでそれを記録する。
lowvram オプション
私は、GTX1080ti を画像生成のために割り当てているが、VRAM が約 11GB 程度ある中で、lowvram オプションが付いていると、せいぜい数 GB 程度しか使わない状態で、GPU自体も 30% 程度しか使えていなかったりと、全体的に動作が遅かった。
またモデルがメインメモリの方に読み込まれてしまうからか、画像生成だけで初回で、20GB程度持っていかれて、その後は使い込むほど WebUI ごと再起動しない限り、メモリリークを起こして食いつぶして行く様相だった。
このような状況では、webui.conf から使いたいモデルが VRAM 内に収まっているとわかっているなら、デフォルトで AUR からインストールしたときには付いている、--lowvram を消したほうがいいかもしれない。ちなみにこのオプションを消すと、メインメモリの使用率は圧倒的に下がるが、変わりに GPU のメモリをいっぱい使うようになる。
画像生成はせずモデルがロードされた様子の例
# nvidia-smi
Sun Sep 14 01:02:25 2025
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 580.82.09 Driver Version: 580.82.09 CUDA Version: 13.0 |
+-----------------------------------------+------------------------+----------------------+
| GPU Name Persistence-M | Bus-Id Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan Temp Perf Pwr:Usage/Cap | Memory-Usage | GPU-Util Compute M. |
| | | MIG M. |
|=========================================+========================+======================|
| 0 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti Off | 00000000:07:00.0 On | N/A |
| 36% 46C P8 13W / 250W | 8845MiB / 11264MiB | 10% Default |
| | | N/A |
+-----------------------------------------+------------------------+----------------------+
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| Processes: |
| GPU GI CI PID Type Process name GPU Memory |
| ID ID Usage |
|=========================================================================================|
| 0 N/A N/A 1504 G /usr/lib/Xorg 303MiB |
| 0 N/A N/A 1867 G /usr/bin/gnome-shell 60MiB |
| 0 N/A N/A 7409 C+G ...b/gnome-remote-desktop-daemon 298MiB |
| 0 N/A N/A 467649 C ...ffusion-webui/venv/bin/python 7726MiB |
| 0 N/A N/A 1984341 G ...ersion=20250910-180038.780000 430MiB |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
画像生成中の例
# nvidia-smi
Sun Sep 14 01:05:49 2025
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 580.82.09 Driver Version: 580.82.09 CUDA Version: 13.0 |
+-----------------------------------------+------------------------+----------------------+
| GPU Name Persistence-M | Bus-Id Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan Temp Perf Pwr:Usage/Cap | Memory-Usage | GPU-Util Compute M. |
| | | MIG M. |
|=========================================+========================+======================|
| 0 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti Off | 00000000:07:00.0 On | N/A |
| 41% 67C P2 236W / 250W | 9656MiB / 11264MiB | 100% Default |
| | | N/A |
+-----------------------------------------+------------------------+----------------------+
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| Processes: |
| GPU GI CI PID Type Process name GPU Memory |
| ID ID Usage |
|=========================================================================================|
| 0 N/A N/A 1504 G /usr/lib/Xorg 303MiB |
| 0 N/A N/A 1867 G /usr/bin/gnome-shell 93MiB |
| 0 N/A N/A 7409 C+G ...b/gnome-remote-desktop-daemon 298MiB |
| 0 N/A N/A 467649 C ...ffusion-webui/venv/bin/python 8666MiB |
| 0 N/A N/A 1984341 G ...ersion=20250910-180038.780000 268MiB |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
結局メモリリークする例
GPU 側にモデルを読み込むようになり、メインメモリをあまり使わなくなっても、起動したてのときは、1 GB も使ってなかった気がするが、このようにして使い込むほどにだんだんと、何 GB も食いつぶし始める。
定期的に再起動したり、メモリ使用が一定を超えたら、自動的に kill して再起動するとか、そういう工夫が必要であることに変わりはないようである。
● stable-diffusion-webui.service - Stable Diffusion Web UI
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/stable-diffusion-webui.service; enabled; preset: disabled)
Drop-In: /etc/systemd/system/stable-diffusion-webui.service.d
└─override.conf
Active: active (running) since Thu 2025-09-11 21:40:13 JST; 2 days ago
Invocation: 478bf01465a74b3aa9632b822857dc0b
Main PID: 467428 (accelerate)
Tasks: 92 (limit: 629145)
Memory: 8.2G (max: 20G, available: 11.7G, peak: 8.6G)
CPU: 23h 31min 19.092s
CGroup: /system.slice/stable-diffusion-webui.service
├─467428 /opt/stable-diffusion-webui/venv/bin/python /opt/stable-diffusion-webui/venv/bin/accele>
└─467649 /opt/stable-diffusion-webui/venv/bin/python /opt/stable-diffusion-webui/launch.py --dat>
systemd メモリ制限
どうやっても、メモリリークするし、それでメインメモリを全部食いつぶされて、linux がフリーズして強制的に再起動するまで、HDD が永遠にガリガリいうみたいな光景は、まさしくハードウェアの寿命を無駄にしているって感じで嫌だしうざいので、Systemd 側でメモリ使用に制限をかけてしまうことにした。
AUR にある stable-diffusion-webui にはすでに systemd のサービスがデフォルトで用意されているので、ChatGPT-5 にそのことを投げたら、追加設定がアプデ時に毎回上書きされないように、drop-in 設定を使えと帰ってきて、実際試してみてそれが動いたため、今回はそれを採用した。
追加した設定
Service の項目に、メモリ管理の有効化と、メモリの最大の設定や、OOM Killer が優先的にメモリが足りなくなったら stable-diffusion-webui を Kill するように、スコアを設定したりした。
[Service]
MemoryAccounting=true
MemoryMax=20G # メモリ上限 20GB。 本当は 5GB 程度でいいかもしれない
OOMScoreAdjust=1000 # 1000 で最も優先的に Kill されやすくなり、 -1000 で Kill されなくなるとのこと。
既存の systemd サービスをオーバーライドする方法
# エディタが立ち上がるので、追加したい設定項目で全部上書きする。
sudo systemctl edit stable-diffusion-webui.service
# 正常に設定が反映されたときは以下のように、メッセージが出てくる
Successfully installed edited file '/etc/systemd/system/stable-diffusion-webui.service.d/override.conf'.
stable-diffusion-webui.service オーバーライド例
### Editing /etc/systemd/system/stable-diffusion-webui.service.d/override.conf
### Anything between here and the comment below will become the contents of the drop-in file
# ここに上書き設定を書く ------------------------------------
# ここに上書き設定を書く ------------------------------------
[Service]
MemoryAccounting=true
MemoryMax=20G
OOMScoreAdjust=1000
# ここに上書き設定を書く ------------------------------------
# ここに上書き設定を書く ------------------------------------
### Edits below this comment will be discarded
# ここからしたに書いても何も反映されず、消されてしまう。
### /usr/lib/systemd/system/stable-diffusion-webui.service
# [Unit]
# Description=Stable Diffusion Web UI
# After=network.target
#
# [Service]
# Type=simple
# User=sdwebui
# Group=sdwebui
# WorkingDirectory=/opt/stable-diffusion-webui
# Environment=PYTHONUNBUFFERED=1
# EnvironmentFile=/etc/stable-diffusion-webui/webui.conf
# ExecStart=/bin/bash -c '\
# : "${DATA_DIR:=/var/opt/stable-diffusion-webui}"; \
# srcdir="/usr/share/stable-diffusion-webui/models/Stable-diffusion"; \
# destdir="${DATA_DIR}/models/Stable-diffusion"; \
# modelfile="v1-5-pruned-emaonly.safetensors"; \
# mkdir -p "$destdir" && \
# [ ! -f "$destdir/$modelfile" ] && cp "$srcdir/$modelfile" "$destdir/"; \
# exec /opt/stable-diffusion-webui/venv/bin/accelerate \
# launch ${ACCELERATE_FLAGS:+$ACCELERATE_FLAGS} \
# /opt/stable-diffusion-webui/launch.py \
# --data-dir "$DATA_DIR" ${WEBUI_FLAGS:+$WEBUI_FLAGS}'
#
# Restart=always
# StartLimitInterval=120
# StartLimitBurst=15
# UMask=007
#
# [Install]
# WantedBy=multi-user.target
ChatGPT-5 以外の参考
正直 ChatGPT は平気で変なことを堂々と言ってきて、どれが正しい、それは絶対間違ってるみたいな、あたかも確かなことを言っているかのような言い方してきて鬱陶しく、非常に私はそれに対し疑心暗鬼でもあるので、自分でも OOMScoreAdjust についての説明が ChatGPT の出力したこととおかしくないかとか、適当にぼちぼちネットを調べたりした。
以下は、似たような systemd でメモリ管理をしたいケースにおいて、参考になりそうなサイトでもあると思われる。
- systemd.resource-control
https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/latest/systemd.resource-control.html (2025年9月14日) - systemd memory limit not working/example - Unix & Linux Stack Exchange
https://unix.stackexchange.com/questions/449210/systemd-memory-limit-not-working-example (2025年9月14日) - systemd.exec
https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/latest/systemd.exec.html (2025年9月14日)
GPU のファン速度の設定
画像生成で GPU に負荷をかけまくると、私の環境の場合、どうもデフォルトのファン回転数制御では、85℃ あたりでうろつきながら、サーマルスロットリングって感じで、電力にはまだ余裕があるのに、GPU の性能を使い切れないという現象が起こることがわかった。
気づいた過程としては、
- 画像生成を始めて最初は、徐々に40℃あたりから温度が上がっていき、パワーリミットで 240w/250w という感じで動いている
- 数分後には、80℃以上に達し、190w/250w という感じでサーマルスロットリングでうろつくようになる
ということがあった。
| 温度 | ファン速度 | 電力 | パワーリミット | サーマルスロットリング | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生成をしていないとき | 40℃ | 30%くらい? | 20~60w | なし | なし |
| 生成はじめ | 40℃から上昇 | 徐々に上昇 | 240w~260w | あり(250w) | なし |
| 生成を始めて数分後 | 85℃あたりをうろつく | 65% | 180w~200w | なし | あり |
最初は単に画像生成AIとはそういうものなのだと思っていたが、段々と温度と消費電力の関係をぼーっとなんとなく見ていたら、おかしいなと気づいた。
ここでは具体的にどうやって、nvidia 製 GPU のファンの速度を linux 上で nvidia-settings コマンドを使って制御するか記録しようと思う。
-c 0 って何?
sudo nvidia-settings -a ‘[fan:0]/GPUTargetFanSpeed=100’
# Authorization required, but no authorization protocol specified
#
#
# ERROR: The control display is undefined; please run `nvidia-settings --help` for usage information.
-c を指定しなかったときの、上記のエラーに従って、調べてみると、以下のようなことが書かれていた。
nvidia-settings --help
# ...
# -c CTRL-DISPLAY, --ctrl-display=CTRL-DISPLAY
# Control the specified X display. If this option is not given, then nvidia-settings will control the di
# splay specified by '--display'; if that is not given, then the $DISPLAY environment variable is used.
# ...
どうも、明示的に GPU が制御している X11 の画面を指定する必要があるようで、SSH 経由でリモートで作業していたのも相まって、nvidia-settings が $DISPLAY 環境変数からも何も得られなかったようである。
よくわからなければ、0 ~ 10 くらいまで試していれば多分いつか当たると思われ、特殊な構成にしていなければ、X11 のディスプレイは基本 0 番に描画されるようになっているので、そこをまず当たればいいと思われる。
設定できるファンを調べる
sudo nvidia-settings --query fans -c 0
# Authorization required, but no authorization protocol specified
#
#
# 1 Fan on 0
#
# [0] [fan:0] (Fan 0)
#
# Has the following name:
# FAN-0
ファン回転数を 0~100 % の間で設定する
sudo nvidia-settings -c 0 -a [fan:0]/GPUTargetFanSpeed=100
# Authorization required, but no authorization protocol specified
#
#
# Attribute 'GPUTargetFanSpeed' ([fan:0]) assigned value 100.
ファンを最大回転数で回してみた様子
ざっと、5℃ 程度の温度低下が見られた。パワーリミットで再び動作するようになったりと効果はあるようである。しかし、ファンのベアリングの寿命を考えると、正直あんまりこういう強引なやり方はよくないかもしれないので、使っているとき以外はファン制御は GPU に返したほうがいいかも。
# nvidia-smi
Sun Sep 14 02:59:16 2025
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 580.82.09 Driver Version: 580.82.09 CUDA Version: 13.0 |
+-----------------------------------------+------------------------+----------------------+
| GPU Name Persistence-M | Bus-Id Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan Temp Perf Pwr:Usage/Cap | Memory-Usage | GPU-Util Compute M. |
| | | MIG M. |
|=========================================+========================+======================|
| 0 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti Off | 00000000:07:00.0 On | N/A |
|100% 80C P2 253W / 250W | 9574MiB / 11264MiB | 100% Default |
| | | N/A |
+-----------------------------------------+------------------------+----------------------+
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| Processes: |
| GPU GI CI PID Type Process name GPU Memory |
| ID ID Usage |
|=========================================================================================|
| 0 N/A N/A 1504 G /usr/lib/Xorg 353MiB |
| 0 N/A N/A 1867 G /usr/bin/gnome-shell 60MiB |
| 0 N/A N/A 7409 C+G ...b/gnome-remote-desktop-daemon 298MiB |
| 0 N/A N/A 467649 C ...ffusion-webui/venv/bin/python 8668MiB |
| 0 N/A N/A 759787 G /usr/bin/kgx 7MiB |
| 0 N/A N/A 760274 G nvidia-settings 2MiB |
| 0 N/A N/A 1984341 G ...ersion=20250910-180038.780000 155MiB |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
GPU にファン制御を返す
sudo nvidia-settings -c 0 -a GPUFanControlState=0
手動のファン回転数指定から、元の自動制御に戻す方法についても調べてみた。とは言ってもどうすればいいかわからないので、とりあえず、 そこで、Fan についてどういう項目があるか調べてみると以下のようになった。 それで、試行錯誤と結局ググる過程
nvidia-settings --help してみると、以下の項目が気になった。nvidia-settings --help
# ...
# -e DESCRIBE, --describe=DESCRIBE
# Prints information about a particular attribute. Specify 'all' to list the descriptions of all attribu
# tes. Specify 'list' to list the attribute names without a descriptions.
# ...
nvidia-settings -e all | grep Fan
# Attribute 'GPUFanControlState':
# Attribute 'GPUTargetFanSpeed':
# Attribute 'GPUCurrentFanSpeed':
# Attribute 'GPUResetFanSpeed':
# Attribute 'GPUCurrentFanSpeedRPM':
# Attribute 'GPUFanControlType':
# Attribute 'GPUFanTarget':
GPUFanControlState や GPUFanControlType あたりが怪しそうだと思い、更に調べてみる。nvidia-settings -e GPUFanControlState
# Attribute 'GPUFanControlState':
# - Attribute value is an integer.
# - Attribute is not written to the rc file.
# The current fan control state; the value of this attribute controls the availability of additional fan
# control attributes. Note that this attribute is unavailable unless fan control support has been enabled by
# setting the "Coolbits" X config option.
nvidia-settings -e GPUFanControlType
# Attribute 'GPUFanControlType':
# - Attribute value is an integer.
# - Attribute is not written to the rc file.
# Returns how the GPU fan is controlled. '1' means the fan can only be toggled on and off; '2' means the fan
# has variable speed. '0' means the fan is restricted and cannot be adjusted under end user control.
GPUFanControlState あたりを試してみるも、どういう値にすればいいかまでは、コマンドのヘルプを見てもわからなかったので、適当にネットで調べて、GPUFanControlState=0 に至る。nvidia-settings -e GPUFanControlState
# Attribute 'GPUFanControlState':
# - Attribute value is an integer.
# - Attribute is not written to the rc file.
# The current fan control state; the value of this attribute controls the availability of additional fan
# control attributes. Note that this attribute is unavailable unless fan control support has been enabled by
# setting the "Coolbits" X config option.
参考
- How to set fanspeed in Linux from terminal - CUDA / CUDA Programming and Performance - NVIDIA Developer Forums
https://forums.developer.nvidia.com/t/how-to-set-fanspeed-in-linux-from-terminal/72705/6 (2025年9月14日) - Little tip for super easy GPU fan control without any software : r/linux_gaming
https://www.reddit.com/r/linux_gaming/comments/1gk4676/little_tip_for_super_easy_gpu_fan_control_without/ (2025年9月14日)
WebUI の初期値を変更する (2025/10/20)
しばらくいろんな画像を生成して遊んでいたところ、だんだんとデフォルトの設定値が気に食わなくなった。それで、いちいち画像生成時に設定を変更するのはめんどくさかったので、設定する方法について調べていた。すでにいろんな解説記事があるが、自分用の記録としてやり方をここに書く。
data フォルダ内の ui-config.json を変更する
今回は部分的に、以下の項目の設定を txt2img に注目して変更する例を挙げる。data フォルダとは、コンフィグの設定例webuiconfの説明で出てくるDATA_DIRのことである。
- 解像度 512x512 -> 1200x1200
- ステップ数 20 -> 35
- バッチカウント 1 -> 10
{
...
"customscript/sampler.py/txt2img/Sampling steps/visible": true,
"customscript/sampler.py/txt2img/Sampling steps/value": 35, // 変更した部分
"customscript/sampler.py/txt2img/Sampling steps/minimum": 1,
"customscript/sampler.py/txt2img/Sampling steps/maximum": 150,
"customscript/sampler.py/txt2img/Sampling steps/step": 1,
"txt2img/Width/visible": true,
"txt2img/Width/value": 1200, // 変更した部分
"txt2img/Width/minimum": 64,
"txt2img/Width/maximum": 2048,
"txt2img/Width/step": 8,
"txt2img/Height/visible": true,
"txt2img/Height/value": 1200, // 変更した部分
"txt2img/Height/minimum": 64,
"txt2img/Height/maximum": 2048,
"txt2img/Batch count/visible": true,
"txt2img/Batch count/value": 10, // 変更した部分
"txt2img/Batch count/minimum": 1,
"txt2img/Batch count/maximum": 100,
"txt2img/Batch count/step": 1,
...
}
stable-diffusion-webui を再起動する
私の環境で試したところ、webui を再起動するまでは、ui-config.jsonの変更が反映されないことが分かったため、再起動するようにしていた。
sudo systemctl restart stable-diffusion-webui
参考
- 【Stable Diffusion WebUI 】 ui-config 活用法。SDXL に合わせて設定を最適化+デフォルト設定を変更してみた! #AI - Qiita
https://qiita.com/tonosamart/items/23a612768098870c20ae (2025年10月20日)
Stable-diffusion の進捗状況を取得する (2025/10/21)
WebUIを閉じてしまうと、今動かしているジョブの進捗状況が確認できないということがあったので、ChatGPTに適当に聞いてみて、出てきたのを試してみた。進捗状況はWebUIを閉じてしまっても、少なくとも私の環境では、以下のURLでJSON形式で取得できるようである。
domain.name.or.ip.addressについては、ローカルで動いている webui のアドレスである。
https://domain.name.or.ip.address/sdapi/v1/progress
{
"progress": 0.9414285714285715,
"eta_relative": 73.19720708907812,
"state": {
"skipped": false,
"interrupted": false,
"stopping_generation": false,
"job": "Batch 10 out of 10",
"job_count": 10,
"job_timestamp": "20251021221750",
"job_no": 9,
"sampling_step": 12,
"sampling_steps": 35
},
"current_image": "ImageBlobString",
"textinfo": null
}
一応調べてみると、以下の githubのDiscussionsのところにあったスレッドになんか書いてあることは確認できた。
- Progress API endpoint · AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui · Discussion #7888
https://github.com/AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui/discussions/7888 (2025年10月21日)
またもう少し、どんなエントリーポイントがあるのかリストがないか調べてみたところ、ローカルで動かしているサーバに以下のURLでアクセスすることで利用できるAPIのリストを得られるようである。
https://domain.name.or.ip.address/docs
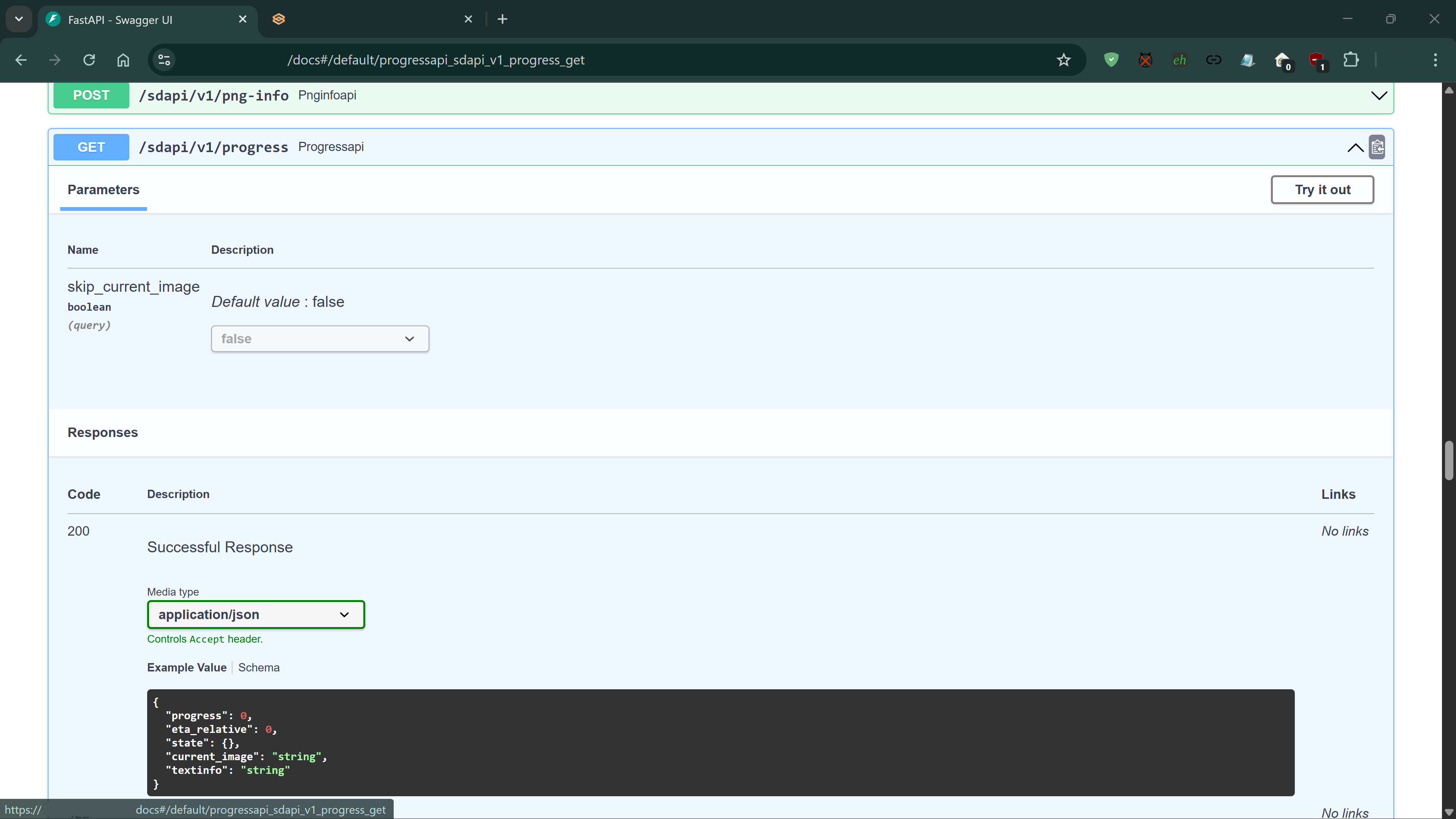
- Basic Documentation and Examples for using API · AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui · Discussion #3734
https://github.com/AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui/discussions/3734 (2025年10月21日)
メモリ管理を何とかする (2026/1/29)
以前メモリ管理について、メインメモリを stable-diffusion-webui がリークしているみたいなことをこの記事で書いていて、それについて最近進展があったので、記録を取る。具体的には、tcmallocを導入することについて記録する。
ライブラリのインストール
yay -S gperftools
#sudo pacman -S gperftools
yay -Ql gperftools
...
gperftools /usr/lib/libtcmalloc.so
...
systemd で環境変数を設定してtcmallocを使うようにする
sudo systemctl edit stable-diffusion-webui.service
### Editing /etc/systemd/system/stable-diffusion-webui.service.d/override.conf
### Anything between here and the comment below will become the contents of the drop-in file
# ここに上書き設定を書く ------------------------------------
# ここに上書き設定を書く ------------------------------------
[Service]
MemoryAccounting=true
MemoryMax=20G
OOMScoreAdjust=1000
Environment="LD_PRELOAD=/usr/lib/libtcmalloc.so"
# ここに上書き設定を書く ------------------------------------
# ここに上書き設定を書く ------------------------------------
### Edits below this comment will be discarded
# ここからしたに書いても何も反映されず、消されてしまう。
### /usr/lib/systemd/system/stable-diffusion-webui.service
# [Unit]
# Description=Stable Diffusion Web UI
# After=network.target
#
# [Service]
# Type=simple
# User=sdwebui
# Group=sdwebui
# WorkingDirectory=/opt/stable-diffusion-webui
# Environment=PYTHONUNBUFFERED=1
# EnvironmentFile=/etc/stable-diffusion-webui/webui.conf
# ExecStart=/bin/bash -c '\
# : "${DATA_DIR:=/var/opt/stable-diffusion-webui}"; \
# srcdir="/usr/share/stable-diffusion-webui/models/Stable-diffusion"; \
# destdir="${DATA_DIR}/models/Stable-diffusion"; \
# modelfile="v1-5-pruned-emaonly.safetensors"; \
# mkdir -p "$destdir" && \
# [ ! -f "$destdir/$modelfile" ] && cp "$srcdir/$modelfile" "$destdir/"; \
# exec /opt/stable-diffusion-webui/venv/bin/accelerate \
# launch ${ACCELERATE_FLAGS:+$ACCELERATE_FLAGS} \
# /opt/stable-diffusion-webui/launch.py \
# --data-dir "$DATA_DIR" ${WEBUI_FLAGS:+$WEBUI_FLAGS}'
#
# Restart=always
# StartLimitInterval=120
# StartLimitBurst=15
# UMask=007
#
# [Install]
# WantedBy=multi-user.target
関係のありそうなページ
参考にしたサイトとか
-
AUR (en) - stable-diffusion-webui
https://aur.archlinux.org/packages/stable-diffusion-webui (2025年7月12日) -
[Bug]: Error: Connection errored out. · Issue #9074 · AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui
https://github.com/AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui/issues/9074 (2025年7月12日) -
node.js - WebSockets and Apache proxy: how to configure mod_proxy_wstunnel? - Stack Overflow
https://stackoverflow.com/questions/27526281/websockets-and-apache-proxy-how-to-configure-mod-proxy-wstunnel (2025年7月12日) -
mod_proxy_wstunnel - Apache HTTP Server Version 2.4
https://httpd.apache.org/docs/current/mod/mod_proxy_wstunnel.html (2025年7月12日) -
apache - .htaccess: Invalid command ‘RewriteEngine’, perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration - Stack Overflow
https://stackoverflow.com/questions/10144634/htaccess-invalid-command-rewriteengine-perhaps-misspelled-or-defined-by-a-m (2025年7月12日) -
How can I access the web UI of Stable Diffusion on my PC from another device in my home network? : r/HomeNetworking
https://www.reddit.com/r/HomeNetworking/comments/ybfhp6/how_can_i_access_the_web_ui_of_stable_diffusion/ (2025年7月13日) -
ChatGPT
https://chatgpt.com/ (2025年7月12日) -
Memory leak when using SDXL in the latest version of webui automatic111111 : r/StableDiffusion
https://www.reddit.com/r/StableDiffusion/comments/1bq2py3/memory_leak_when_using_sdxl_in_the_latest_version/ (2025年9月14日) -
Insane memory leak · Issue #2219 · lllyasviel/stable-diffusion-webui-forge
https://github.com/lllyasviel/stable-diffusion-webui-forge/issues/2219 (2025年9月14日) -
systemd.resource-control
https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/latest/systemd.resource-control.html (2025年9月14日) -
systemd memory limit not working/example - Unix & Linux Stack Exchange
https://unix.stackexchange.com/questions/449210/systemd-memory-limit-not-working-example (2025年9月14日) -
systemd.exec
https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/latest/systemd.exec.html (2025年9月14日) -
How to set fanspeed in Linux from terminal - CUDA / CUDA Programming and Performance - NVIDIA Developer Forums
https://forums.developer.nvidia.com/t/how-to-set-fanspeed-in-linux-from-terminal/72705/6 (2025年9月14日) -
Markdown Table Generator · Table to Markdown
https://tabletomarkdown.com/generate-markdown-table/ (2025年9月14日) -
【Stable Diffusion WebUI 】 ui-config 活用法。SDXL に合わせて設定を最適化+デフォルト設定を変更してみた! #AI - Qiita
https://qiita.com/tonosamart/items/23a612768098870c20ae (2025年10月20日) -
Progress API endpoint · AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui · Discussion #7888
https://github.com/AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui/discussions/7888 (2025年10月21日) -
Basic Documentation and Examples for using API · AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui · Discussion #3734
https://github.com/AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui/discussions/3734 (2025年10月21日) -
Google Gemini
https://gemini.google.com/app/d715508dd982e7fe (2026年1月29日)